4研究部のご紹介
次世代医療開発センター(HBI)
2021年春以降、HBIの新たな環境のもとで研究活動を推進する研究部の代表者にクローズアップ。それぞれの研究活動をご紹介いただきます。新設の「感染症制御研究部」では、研究テーマや今後に向けた展望などについても語っていただきました。
免疫機構研究部太田 明夫部長
炎症性疾患に苦しむ患者さんを救う研究を推進
免疫というものは、私たちが生存していく上で欠くことのできないものであり、そこに不具合が生じると多岐にわたる疾患の原因となります。その中には自己免疫疾患、アレルギー性疾患、さらに感染症、がんなども含まれます。免疫のシステムの中には、その反応の仕方を調節するメカニズムがあらかじめ備わっています。私たちは、そのメカニズムを標的として、免疫を適切にコントロールする方法を研究しています。その成果が医療応用され、病気で苦しむ人びとを救う力になれるものを生み出すことが目標です。
詳しくはこちらから▶︎

神経変性疾患研究部星 美奈子部長
誰もが最期まで健やかな人生を送れる社会を目指す
ヒトの脳は、これまでの経験に基づいて判断基準となる「私らしさ」を決めています。アルツハイマー病を始めとする神経変性疾患では、脳の中で「神経細胞」が死ぬことで、この私らしさが失われていきます。私たちは、神経細胞死の原因分子を発見し、細胞死のメカニズムを分子レベルで解明しつつあり、新たな治療薬の開発にも多角的に取り組んでいます。神戸発の研究により、疾患を正しく理解し、それを防ぎ、最期まで健やかに私らしく人生を歩める、そういう社会を次世代に残していきたいと思っています。
詳しくはこちらから▶︎
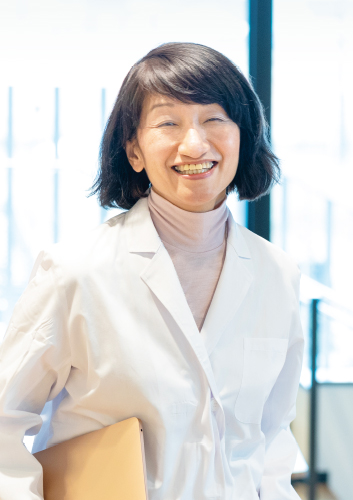
血液・腫瘍研究部井上 大地上席研究員(グループリーダー)(北村 俊雄 客員部長)
血液がんのメカニズムをひも解き、革新的医療につなげる
私たちの研究部は、急性白血病などの血液のがんについて、未知のメカニズムを解き明かし、新しい治療法を開発することを目的に発足しました。従来の常識にとらわれず、統合的な視点からがんを捉えることにより、ベッドサイドに還元することを目指しています。私たちが見つけた細胞レベル・遺伝子レベルでの新しい生命現象に基づいて、メカニズムに則した治療応用を試みています。このような研究により、新たに救える命があると信じて研究を進めています。
詳しくはこちらから▶︎
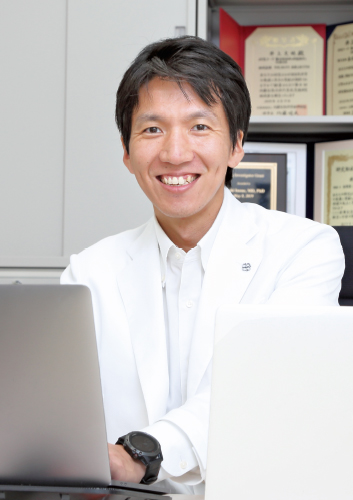
感染症制御研究部
感染研と機構の連携を強め、感染症創薬基盤開発を加速
大学院時代に抗体遺伝子書き換え分子AIDを発見
私たちの免疫系は、AIDという分子が抗体遺伝子を書き換えることで抗体の機能を強化し、病原体を排除しています。私は本庶先生の研究室に参加していた大学院生時代に、当時、未知の分子だったAIDを見つけ、以来ずっとAID研究を行ってきました。AIDによる遺伝子書き換えは時に失敗が起こり、がんの原因になります。本庶研究室を離れ金沢大に移る時、本庶先生に「研究者が独立する時は自分自身の大海原を開拓すべし」と言われ、興味のあったウイルスとがんに着目。現在は国立感染症研究所で、遺伝子変化とウイルス発がんの発生機構解明の研究を進めています。
感染症制御研究部は「ウイルス発がん」「創薬基盤開発」「感染症研究」が主な研究テーマ
感染症制御研究部が推進していく研究は3つあります。まず1つは、B型肝炎ウイルスとヒトパピローマウイルスなど腫瘍ウイルスが、がんを起こすメカニズムを解明すること。2つめは、そこから発展して診断・治療薬やワクチンの開発など、実用化に向けた基盤研究に着手することです。これは病院や医療関連企業、研究機関が集積している神戸医療産業都市だからこそ、積極的にアプローチできるのではと大変期待しています。3つめは社会的ニーズの高いウイルス感染症の研究です。私は新型コロナウイルスは専門ではありませんが、新型コロナウイルス研究は社会のニーズが高く、HBIが求められる研究施設になるという意味でも取り組んでいくべきテーマだと考えます。
感染研と機構の橋渡しにより創薬を実現する
本庶先生から新研究部の立ち上げに関わってほしいというお話をいただいた時は、率直に嬉しかったです。先生の下でドキドキハラハラと毎日を過ごした、駆け出し研究者時代を思い出しました。神戸では、価値観を共有できる人たちと同じ目標に向かって走れると思うと、モチベーションが上がります。感染研が持つユニークな研究素材と機構の力強い橋渡しのリソースを組み合わせ、創薬やワクチン開発のための基盤開発を行っていきたいと思います。
詳しくはこちらから▶︎
MESSAGE
感染症制御研究部 村松 正道客員部長
アウトリーチ活動では、出前授業や動画配信などを通して、中高生などにサイエンスのおもしろさも伝えたいですね。
Profile小児科研修後、本庶佑研究室にて研究をスタート。12年間AIDを研究し、2007年に金沢大学医学部教授就任。現在は国立感染症研究所に所属しながら新研究部の立ち上げを助力。






