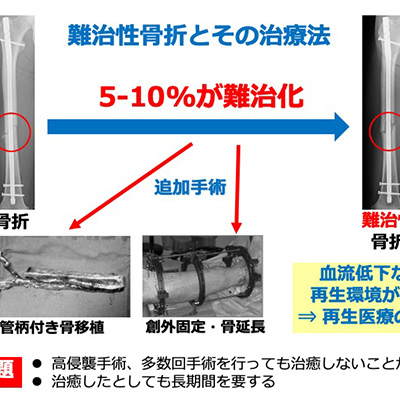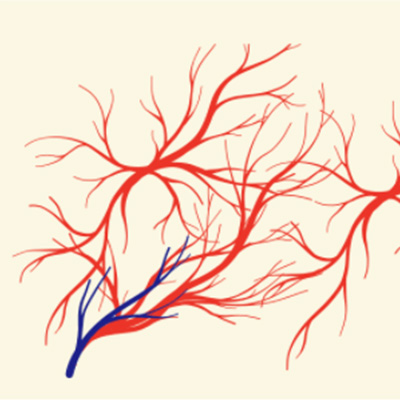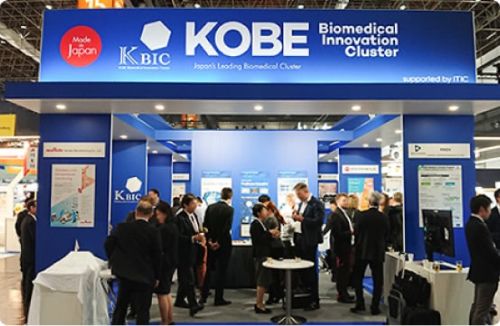2025.08.29
- 企業・研究者向け
- 医療関係者向け
詳細な内容
神戸先端医療研究センターは、新しい医療に繋がりうる基礎研究、正常と病気を理解する研究、臨床試験まで行った研究など、幅広く医学生物学研究の講演等を企画してまいります。研究者・技術者の参加をお待ちしております。
【プログラム】
◆講 師
清野 研一郎 先生
北海道大学遺伝子病制御研究所
免疫生物分野 教授
◆演 題
移植免疫寛容研究の最先端〜多能性幹細胞が持つ免疫寛容誘導能の発見〜
◆内 容
免疫寛容は、特定抗原に対して免疫応答が誘導されない状態を指し、移植免疫学において重要な概念である。1953年、Medawarらは、胎生期あるいは新生仔期の免疫系発達初期に外来抗原を暴露すると、その抗原に対して後の生涯にわたり免疫応答が起こらないことを実験的に示し、免疫寛容の概念を確立した。これは免疫抑制剤などによる継続的な治療を必要としない現象であり、その後の移植研究における重要な理論的基盤となった。近年、同種異系(他家)のiPS細胞(もしくはES細胞)を用いた移植医療の実用化が期待されている。他家移植において問題になる免疫拒絶反応を抑えるため、主要組織適合抗原(MHC)をノックアウトした低免疫原性iPS細胞などが開発されている。しかし、MHCが一致してもマイナー抗原による拒絶反応は回避困難であり、長期的には免疫抑制剤使用による副作用が問題となる。我々は、他家多能性幹細胞を用いた移植における免疫寛容誘導の可能性についてこれまで検討してきた。その中で最近、同種異系の多能性幹細胞はMHC適合・マイナー抗原不一致のレシピエントに免疫抑制なしに生着しうることを見出した。他家マウスの皮下にiPS細胞もしくはES細胞を接種すると小さなテラトーマが形成された。そこで同レシピエントマウスに二次的に皮膚移植を行った。その結果、驚くべきことに最初に接種した多能性幹細胞と同じ系統の皮膚のみが免疫抑制なしに生着することが判明した。即ち、抗原特異的免疫寛容が誘導された。そのメカニズムを解析したところ、テラトーマ内に発現するTGF-β2とCD25⁺CD103⁺Foxp3⁺エフェクター制御性T細胞(Treg)の存在が重要であることが示された。本研究は、多能性幹細胞そのものがドナー特異的免疫寛容を誘導し得ること、そしてその機序の一端を解明した初めての報告であり、今後の再生医療における免疫制御戦略に新たな視点を提供した。
本講演では、我々が行ってきたこれら免疫寛容研究について紹介するとともに、同研究分野の今後の方向性について議論したい。
会場住所
〒650-0047
神戸市中央区港島南町6丁目3番地の7
お問い合わせ先
神戸医療産業都市推進機構 セミナー事務局
078-306-0708
ibri-seminar@fbri.org
入力者
神戸医療産業都市推進機構